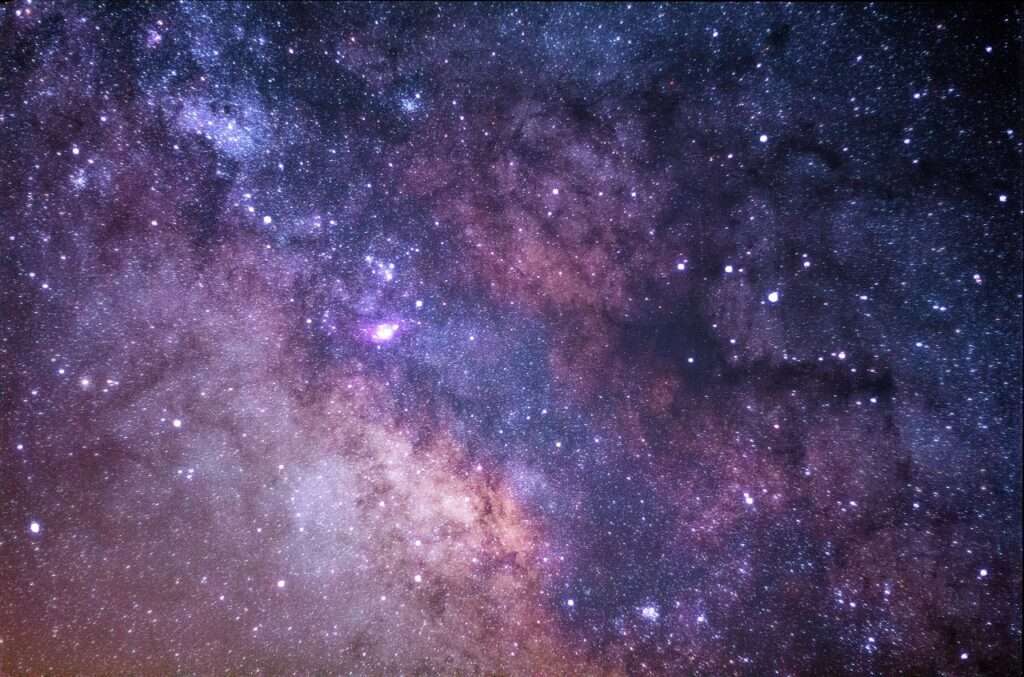 洋一は右のわき腹を抑えた。こみ上げてくる吐き気とどうにもならない倦怠感が彼を支配していた。
洋一は右のわき腹を抑えた。こみ上げてくる吐き気とどうにもならない倦怠感が彼を支配していた。
手を当てた肋骨のいちばん下のあたりはどす黒くが腫れ上がっていた。そんな状態になっても医者へ行かず、薄暗い部屋でじっとしている。肝臓が固くなり、そこにつながる門脈は破裂寸前の状態だったのだ。
もし彼を医者が診たとしたら、それこそ絶対安静と言われたであろう。
もう既に彼自身、わかっていたのかもしれない。精神が極限まで追い詰められ、そこから逃げ出せず、何も食わず、酒に逃げ、内臓が機能しなくなり。意識はしていなかったのかもしれないが、死ぬつもりだったのかもしれない。
洋一は最後にもう一度だけ、漠然とだが迷いを振り切るため、半ば本能的に外に出た。外に出て、よろめきながらも直ヤンの道場を尋ねた。
既に夜の10時を回っており、直ヤンは道着を脱ぎ帰り支度を始めようとしていた。その時、鈍くたたく音に気づき入口の扉を開けた。
洋一がよれたジャージ姿で立っていた。
「よう・いち。来てくれたのか。」と直ヤンが驚いた。
「こんな時間に申し訳ない。稽古をつけてくれ」と洋一が直ヤンを直視してい言った。
直ヤンは洋一の様子が、肉体的にも精神的にも尋常な様子では既にない事を直感した。
だが、洋一の眼差しを受け、そのまま道場の中へ招き入れた。
そして、ロッカーから替えに置いておいた道着を出してきて洋一に手渡した。
「その格好じゃ、さまにならないだろ。これに着替えろ」と洋一言った。
道場の真ん中で、2メートルほどの距離を置き2人が対峙した。次の瞬間、直ヤンが洋一の襟を両手でつかみ投げ飛ばした。投げ飛ばし、畳に洋一の体をたたきつけた。洋一の右のの肩から肩甲骨の辺りから鈍い音がした。
洋一は大の字になった。今の投げで、すでにこれ以上続けることは無理というほど叩き付けられた。
「洋一、立てるか?」と直ヤンが言った。洋一は四つん這いになり、片膝を立て、そして立ち上がった。立ち上がり、そのまま腰を沈めて、頭から直ヤンのタックルした。直ヤンはかわさず、ただ洋一の頭と肩を腹で受け止めた。受け止めてまた洋一を叩き付けた。
「洋一、見ようとするな。見ようとするから迷うんだ。」といって洋一を投げた。関節を取ることもなく、パンチも蹴りも出さず、ただ洋一を投げ続けた。
「考えるな、お前の判断なんか自分を苦しめるだけだ。」投げるたびに洋一に言い聞かせた。「我を忘れろ、手足の感覚も信じるな、感情なんか捨ててしまえ」
また投げた。「変化を全て受け入れてみろ。自分に意思などあると思うな」
なんども同じように襟や袖をつかんで、ただ洋一を投げた。「ただ、没入してみるんだ。
お前なんてものを切り出すな。我をほどけ」投げられながら洋一は、直ヤンが大きな全体に通じる力のように感じていた。
洋一も直ヤンも同乗の真ん中で大の字になって天井を見ていた。
「どうしたらお前みたく強くなれる」と洋一が直ヤンに聞いた。
「高校時代のお前は強かったけどな。だけどいつまでもツッパリの洋一のままじゃ長続きしないぜ。そんな拘りが自分を窮屈にしているんだよ。自我なんてある意味邪念だからな。」と直ヤンが答えた。
「なんていうか、空っぽになった時かな。体が自然に動くんだ。自分を意識している間はどうやっても勝てないんだよ。
何か判断しようとして。だから、どうすればとか、そうゆう事は気にしないでみろよ。何かのおかげとか、そんなことわかりゃしないけど、なんにも期待しないで、意識しないくても、自然に動けるときがあるんだよ。」
「・・・」
「洋一には洋一の、なんていうか、もちまえってのが、たぶんあると思うんだ。なんか空っぽになった時、勝手におっきな力が動かしてくれるんだよ。」
「なんでそんなことわかるの、直ヤンは」
「わからないな。本当にどうなのかは。いままでも稽古したり試合したしてる間、そんな感覚を覚えていたような気はする。ほんとに強いか弱いかなんてわからないけど、自然っていうか混沌とした、何にも無い全体に溶け込むような感じかな。気がつけば試合が終わっているんだよ、いつも」
「柔術みたいに、完全に受け身だな。」洋一はそうつぶやいた。
「計らいを捨てて、もちまえのまま、自然なままでいれば何とかなるよ。お前だけじゃない。俺だってそうだ。周りの人たちも、家族も社会も、国も地球も。」と直ヤンが言った。「でかい話だな。」と洋一が笑った。笑っているうちに、直ヤンの言った「もちまえ」という響きがすっと心にしみてきた。
(自我なんて邪念だったんだ)、そんな思いが洋一の心に浮かんできた。洋一の意識が静かに遠のいて行った。
直ヤンは洋一を背中に担ぎ、車に乗せ、病院ではなく洋一の自宅まで連れ帰った。もう長くないことがわかったからだ。
格闘の世界で相手を倒すことを極めた彼にとっては、同時に相手の身体状態を悟ることにも長けていたといえる。場合によって、それは治すことは同義でもあったのだが、洋一の今の状態は、もはやその域は過ぎていたことが彼にはよくわかった。
洋一はそのまま自宅へ送り届けられ、朝になって意識を戻した。そして、それからの数日間は、静かに過ごした。
粥を作ってもらい出来る限りしっかりと食べ、リビングのソファーの沈み込むように腰掛け、母親とゆっくり会話をし、夜になると自分の部屋に戻り眠りについた。何もない、そうした数日間が洋一にない寄りの救いとなった。
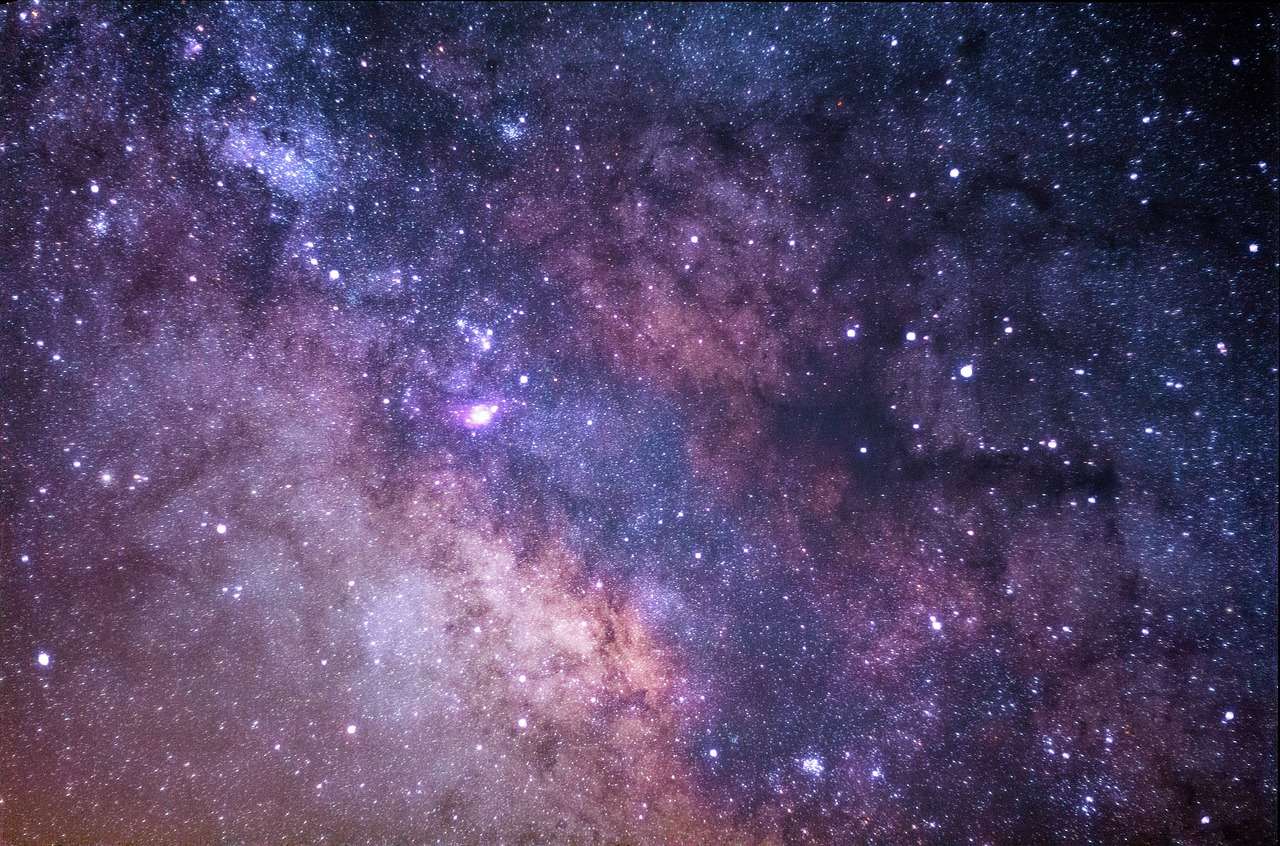
コメント